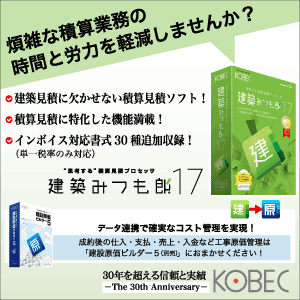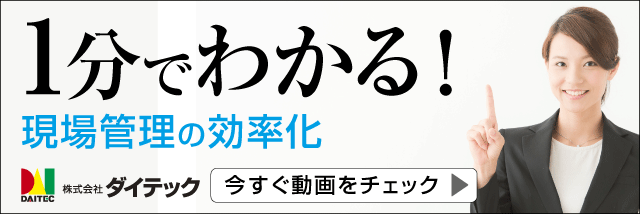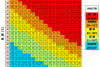「狭いかも…」という不安は造作で解決する!
小さな家を建てるときに一番の不安は「狭くならないか」ということ。収納が足りずモノが散らかるのではないか、家族の居場所が窮屈でお互いの存在がうっとうしくならないか、必要な設備を設置できないのではないか……など心配事は尽きません。
これらを解決するためにおすすめなのが、家具や設備をなるべく「造作」(=造り付け)にすること。特に造作家具は、置き家具よりもムダなスペースが省けます。ゆとりをもって暮らすために、ぜひ造作を検討しましょう。
ここからは、造作を上手に取り入れた事例を4つ紹介します。
アイデア1:スペースにピッタリ納まるソファをつくる
ソファは面積を大きく取るうえに、窓やテレビの位置によっては配置方法が限られてしまいレイアウトに悩むことも。
シーエッチ工房の「ごえんの家」では、窓際に造作のソファを設置。壁にぴったりと寸法を合わせてつくるので、ムダなスペースを省けることはもちろん、小さな空間でも存在感を放ちすぎることなくすっきりと納まります。
窓際につくったことで、外を眺めながらくつろげます。座面を大きめしていることで、デイベッドのような使い方もOK。座面を布張りにしてお気に入りのテキスタイルをセレクトすれば、オリジナリティもアピールできます。
アイデア2:ダイニングテーブルを変形させて大人数でも使いやすく
ダイニングテーブルは、基本的にはキッチンとセットでレイアウトを検討するので、一度置いたらそのまま動かさないことがほとんど。そのためダイニングテーブルを造作するのもおすすめです。
設計島建築事務所の「東中田の家」は、カウンターのようなダイニングテーブルを造作。天板をあえて変形にすることで、椅子を置く位置が限定されず、自由なレイアウトが可能に。造作ソファと組み合わせることで、テーブル周りに余白ができるので移動もスムーズ。
人数を限定しないので複数人で集まりやすいのもメリット。数人で集まって座っても目線が正面でぶつからないので、リラックスして食事が楽しめます。
アイデア3:デッドスペースを活用して小さな作業スペースに
コンパクトな家ではデッドスペースは極力なくしたいものですが、どうしてもできてしまう場所には、棚や机を造作して1つの空間として活用できるようにしましょう。
まちなか山荘(山川建築事務所)の事例では、階段脇のスペースにデスクと棚を造作。子どもの勉強机としたり、趣味や仕事の作業スペースとしたりと、幅広い使い方ができます。奥まった空間でも、窓を設置することで、作業している手元を明るく照らしてくれます。窓から外をのんびりと眺められるのもよいですね。
アイデア4:玄関収納に小さな手洗い場をつくる
新型コロナウイルスの感染拡大によって、需要が増えた「玄関手洗い」。玄関のすぐ近くに小さな洗面台を設けることで、帰宅したらすぐに手を洗えます。「セカンド洗面」とも呼ばれています。Instagramで一気に広まり、定番化しつつある設備です。大塚工務店の「hausi黒壁の角屋」では、玄関収納に洗面を造作。既製品だとサイズが限定されてしまいますが、造作すればその空間にぴったり合わせてつくることができるので、スペースが限られていても大丈夫。また、ほかの造作家具と合わせたデザインにすることで、空間に統一感が生まれます。
いかがでしたでしょうか。造作は注文住宅の醐味でもあります。造作を上手に取り入れて、小さな家でものびのび暮らしやすい家を手に入れてみてはいかがでしょうか。
「#bコレ」Instagramで小さな家の工夫を募集中!
「建築知識ビルダーズ」では、小さな家の写真をInstagramで集めています(詳しくはコチラ)。ハッシュタグ検索 #bコレ小さな家の豊かな暮らし をフォローすれば、今回の記事で紹介したような、上質でこだわりがぎゅっと詰まった事例をたくさんご覧いただけます。ぜひ、フォローして、家づくりの参考にしてください。
工務店や設計事務所の方は、自慢の写真をぜひ投稿ください。ご応募お待ちしています!
ほかのおすすめ記事はコチラ→【省スペースで人気上昇中。壁付けキッチン3つのポイント】