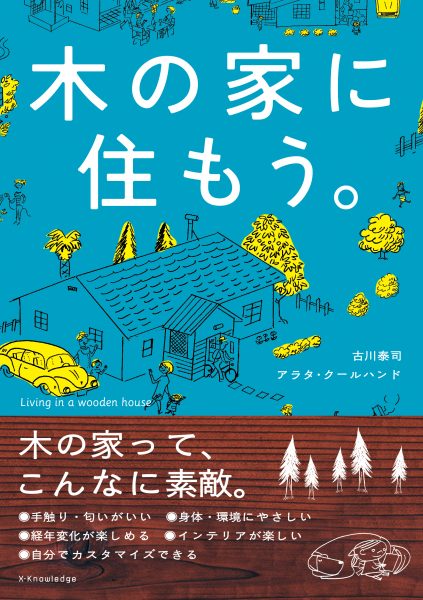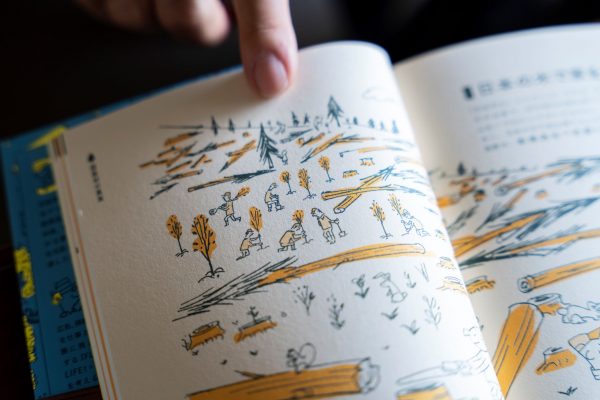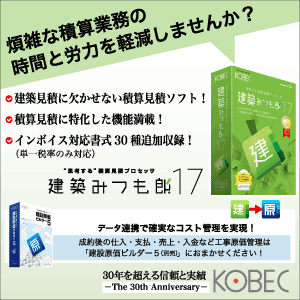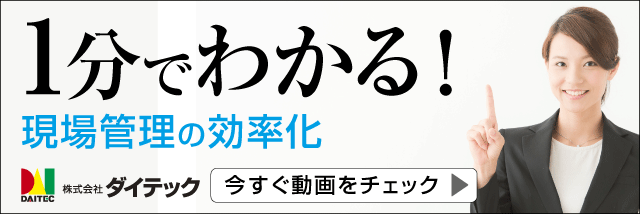〝構造〞と〝防火〞という壁
ワンルームの大空間を成立させるには、構造計画に工夫が求められます。6mを大きく超えるスパンが求められるものの、無垢の製材品では限度があるからです。「わらしべの里共同保育所」では、屋根からの鉛直荷重を無理なく下部へと伝達する必要があり、空間の中央に200㎜角×7mの柱を2本立て、スパンを6m未満にしたうえで、棟木からの鉛直荷重を土台へと伝達しています。
「これらの柱は、3・4・5歳児が過ごす小さな島をつくりつつ、身を寄せる拠り所にもなっています」(古川氏)。
水平構面の設計も大きなポイントとなります。梁間方向で向かい合う耐力壁の間隔が離れてしまい、水平荷重が建物に作用した際、屋根面には大きな力がかかるからです。ここでは、3・4・5歳児室上にある切妻の屋根面は、剛性の高い「JパネルQF」(鳥取CLT)で固めて梁間方向の耐力壁と一体化。水平荷重による屋根面の破壊を予防しています。

準耐火構造(イ準耐)[平12建告1358号]によって内装制限の適用を解除し、木材を露しとする内装を実現[令128条の4第1項][※]。45分の耐火性能が求められる柱・梁・棟木・垂木は、すべて燃え代設計(45㎜)によって断面寸法を決定。30分の耐火性能が求められる屋根は、天井を塗装仕上げとした部分は石膏ボード9㎜厚の2重張り[平12建告1358号第5第1号ハ(2)(ii)]、野地板を露しとした部分は「JパネルQF」(鳥取CLT)を使用した国土交通大臣認定の準耐火構造を採用。軒裏は、面戸板を45㎜厚以上、野地板を30㎜厚以上としている。45分の耐火性能が求められる外壁は、石膏ボード12.5㎜厚の上にガルバリウム鋼板を張り合わせる仕様[平12建告1358号第1第3号ハ(2)]
構造に加えて大きなハードルとなるのが防火。保育所のような特殊建築物では、内装制限という問題が立ちはだかります。今回は、「燃え代設計」による準耐火建築物(イ準耐)として、内装制限の適用を解除しています[令128条の4第1項]。柱と梁は45㎜の燃え代を設け、表面が燃えても構造耐力上支障のない大断面に設定。石膏ボードなどによる防火被覆を用いることなく、木を露しとした木造の準耐火構造を実現しています。

学童室はスキップフロア。棟木を支える通しの丸太柱(φ300㎜)は吉野杉(徳田銘木/奈良県)。棟部の天窓「スカイビューシリーズ VS電動タイプ」(日本ベルックス)からの光が空間全体を包み込む
燃え代設計では、JAS認定の製材であることが条件となります。以前は集成材などに限定されていましたが、平成16年に改正された告示[平12建告1358号]で、含水率15%または20%でJASに適合した製材でも準耐火建築物を建築することが可能となっています。
「埼玉県秩父でJAS製材に長らく取り組んできた金子製材に、基本設計の段階から相談にのってもらい、材をスムーズに調達できました」(古川氏)。

廊下からエントランス方向を見る。明暗のコントラストがはっきりしており、小屋組と床に反射する光が印象的。左側の壁は令114条2項によ る防火上主要な間仕切壁。「15㎜厚の石膏ボード+『エッグウォール』(日本エムテクス)による大壁仕上げです。木材を露しとしないので、柱・梁にはグレードの低い材を使い、コストを抑えています」(古川氏)
「エッグウォール」の施工事例・動画はこちらから。
室内では、柱や梁すべてを露しとする真壁ではなく、一部の梁や防火上主要な間仕切壁[令114条]などは、石膏ボードで覆う大壁としています。こうした部分は燃え代を確保する必要がなく、断面寸法を小さくできるほか、節が多い材料を使えます。
古川氏は「見せる材料と隠す材料を意識して設計しました。丸太を製材すると、節だらけの材がどうしても出てきます。そうした材を壁の中に隠して使えば、山の恵みを無駄なく使えるのです」と説明しています。

ほふく室も学童室と同様のスキップフロア。天井仕上げのスギ羽目板は3層クロスラナパネル「JパネルQF」は国土交通大臣認定を取得した30分準耐火構造の天井仕上げ材であり、屋根断熱材には、ポリエステルを原料とする「パーフェクトバリア」(エンデバーハウス)を使用している
Information
「わらしべの里共同保育所」が生まれたきっかけにもなった『木の家に住みたくなったら』(2011年)は2021年6月、『木の家に住もう。』として大幅に改定されて出版されています。
「本の内容の見直しに当たっては、“木を切る”こと、すなわち“木を使う”ことの大切さを強調しました。それは次世代の森を育てるということ。その想いを表現すべく、木を育てる男の絵を付け加えています」(古川氏)
※ 保育所(児童福祉施設)では、準耐火建築物の場合、「その用途に供する2階の部分の床面積が300㎡以上」であれば内装制限の対象となる。この建物では、2階の床面積が45.54㎡であるため、内装制限の対象とならない。準耐火建築物(耐火建築物)でない場合は、建物全体の床面積が200㎡以上となるため、内装制限の対象となる
取材・文=加藤純・建築知識 建物写真=傍島利浩 書籍写真=平林克己