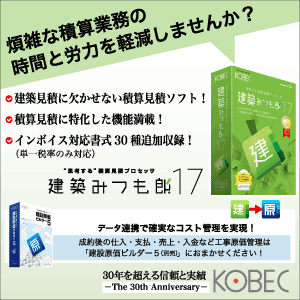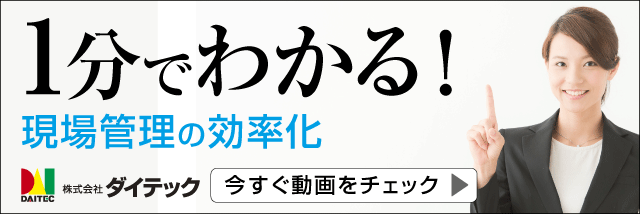実施設計を学べる学校をつくった理由
建築の仕事は、実際に建物を建築してこそ成立するものです。ところが、建築を学ぶときには架空の設計に留まります。しかも多くの場合は基本設計に重点がおかれ、その先の建設まで進まないのが現状です。そのようななかで、「実際の家ができるまでの、すべてを学べるカリキュラム」という独自の建築教育に辿り着きました。
架空の設計と実際に建築することは大きく違い、曖昧さは許されません。材料1つとっても、その選定には責任が生まれます。本校が実施設計の旗を上げ「実際に家を建てる」ことにこだわる理由は、一連の過程から建築の本質に触れるためです。

自らが建築家でもある学校長の仲川孝道氏
バウハウス的な教育の在り方とは?
1919年にドイツで設立された美術学校「バウハウス」は、手工芸と工業化の狭間で試行錯誤しながら、「ものづくり史上」における転換点となりました。なかでも工房課程における技術マイスター制度は斬新な試みであり、工業化時代に即したものづくりの担い手として、【技術的知識のある芸術家】【芸術上の問題を克服できるほどの想像力をもった職人】、その双方を兼ね備えた二刀流の人材育成を目指していたことが分かります。
バウハウスの教育理念は、学生たちの未来の職業像を想定して教育を行うことにあり(時代に翻弄され、目指す方向もカリキュラムも二転三転したが)、産学連携の最も早い成果を上げました。工房課程のなかで生まれた学生作品がプロダクト製品として世に出る一方で、そこでは学校としての在り方が不安視されていたようです。工房はものを量産するだけの工場にあらず、デザイナー育成のための製作実習の場であるとの声を受け、バウハウスは最後まで教育という目的に踏みとどまったのですね。
私たちが「家創りプロジェクト」を継続するのにも苦労があります。教育的立場から理論と技術に適った家を建築しようとすれば、コストがかかりすぎます。だからといって、売れ筋を狙った設計に奔ることや、コストカットのためにやりたいことを削って質を落とすような選択をしてしまえば、そこで教育を諦めなければなりません。学生と共に設計し、地元の建設会社さんと連携してつくる。こうした「職業教育」こそ、大学教育と異なる価値でもあり、バウハウスの如く技術的知識と想像力のバランスの取れた人材を世に送れるのです。
学生時代にどんな力を身に付けるべきか?
建築は本来自由なものですが簡単ではありません。建築はアイデアとサイエンスの結晶です。デザインの中身は果たして理に適っているか、合理性があるか、安全性は担保されているのか、技術的に可能かなど、ある程度の判断材料をもってデザイン(設計)しなければなりません。その判断材料となるのは時に経験であり、また科学的論拠をもとにした知識と、そこから導き出される発想力ともいえるでしょう。
「家創りプロジェクト」では、次に来る問題を乗り越える判断力と協働性が身に付くと考えています。学生が職業像を思い描くとき、自らがどんな力を身につけたのか、そのストーリーこそが重要なカギとなるのではないでしょうか。

現場でものづくりを身近に体感する学生。「経験をできたことが自信となった。社会に出ても怖くはない」と学生たちは話す
現場で活躍できる“職業人“とは?
本校の家創り実践科(4年課程)では他学と同様一通りの建築学を履修した後、一級建築士の教員指導の下で家創りの実務を経験します。現在、市内住宅地に約130 ㎡程度の住宅を設計するプロジェクトが進行しています。確認申請が下り、業者からの見積りを精査し、金額調整したのち、半年ほどをかけて工事が行われます。また、現場では、空間体験、構造体と下地・仕上げ、施工手順、施工方法を見て設計図面と照合します。時に職人の仕事に感心したり、苦労話を聞いたり、いずれも貴重な体験となるでしょう。
最近は家を買うと表現する人が増えました。家は創るもの。建築を仕事とする上で、創造の喜びと建築を実現する術は欠かせません。自分の携わる建築に自信をもつ、そんな職業人を私は育てたいと思います。それがフェリカ家づくり専門学校の存続意義であり、人をつくる教育へのパッションでもあるのです。(談)

「利根川沿いの家Ⅱ」3方向を隣地に囲まれた住宅地に建つ家。現地調査から基本設計がスタート。唯一の東方向は川に向かい開放できることから、1F はプライベートデッキを囲む中庭型のプランとし、2F は眺望重視のプランとなった。実施設計学習期間を経て、この夏から工事着工の予定。学生は自らが描いた図面を手に現場へ通う
連載④「個性が現れる!内装材の選び方」はこちら
取材先「学校法人フェリカ学園 フェリカ家づくり専門学校」
建築・インテリアのプロフェッショナルを育成するための学校。学校側が土地を購入し、設計・施工までを行う超実践な家づくりの教育で注目を集めています。
家創り実践科(4 年制)にて家づくりのAtoZ を学びたい学生を全国から募集。3 年次編入枠有り(対象:大学建築学部卒又は二級建築士所有者のみ)。
※フェリカ建築&デザイン専門学校は2022 年4 月より名称を上記に変更
[公式サイト]https://felica.ac.jp
[所在地]群馬県前橋市南町2-38-2
[TEL]0120-343-750