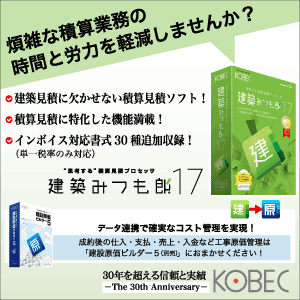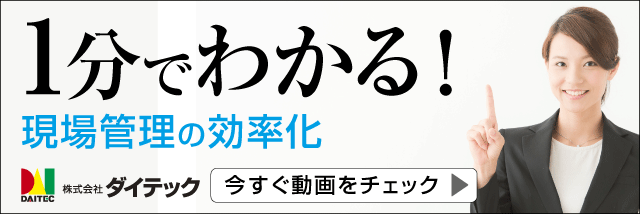同じ空間でも内装材で変わる
家づくりを学ぶ過程で、実物を体感する機会はとても重要。つくる工程を見ることは当然ながら、出来上がったものに対してどう感じるかも重要視したい。たとえば、3,640 ㎜ ×3,640 ㎜の空間を平面図上のただの四角と捉えてはいませんか? 同じ面積でも、天井の高さや視線の抜け、壁の仕上げ、色によって空間の印象は変わります。
学生が実際に家を建てる「家創りプロジェクト」の指導で最も厄介なのは内装材の選定です。数式のように1つの答えを出すのは困難であるため、予め決めたイメージに沿って内装材を選び、選定基準を明確にしていきます。
手順としては、①床・壁・天井の仕上材に求められる機能を学習します。②どのような製品があるのか調べ、比較検討を行います。③壁仕上げの大半はコスト重視でビニルクロスを選ぶことが多いですが、家全体を見渡して2〜3箇所はアクセントとなる壁を設けます。また、色やテクスチャで変化をつけることもあります。
描いた図面と実物を現場で答え合わせ
内装工事の現場で選定するときは、壁紙サンプルを並べて石膏ボードに当てます。そして、光の当たり方や、広面積に張られた状態を想像しながら硬派なイメージになるものを選びます。
「家創りプロジェクト」で実際に建てた「利根川沿いの家」は、スキップフロアで中2階のDKと2階リビングが連続しています。この家では、DKとリビングのオープンな空間の中心にあるL字の壁をアクセントとしました。開放的である一方、落ち着かない空間になってしまう可能性もあったため、L字の壁を重量感のあるマッスな壁面に見立て引き締める効果を狙いました。
マネしたい!内装アイディア11選
ここでは、「利根川沿いの家」で実際に採用したさまざまな内装の組み合わせを紹介します。内装材の組み合わせを変えることで、個性豊かな空間が生まれました。
なかなか想像しにくい内装材の選定は、こうした実験的な進め方によって実地検証し答えを導き出しています。学生にとって結果(どう感じたか、失敗だったのかも含めて)を確認できることが重要で、「家創りプロジェクト」を通して成功体験を積み重ねています。
連載③「地域性を取り入れた住まいの形」はこちら
取材先「学校法人フェリカ学園 フェリカ家づくり専門学校」
建築・インテリアのプロフェッショナルを育成するための学校。学校側が土地を購入し、設計・施工までを行う超実践な家づくりの教育で注目を集めています。
家創り実践科(4 年制)にて家づくりのAtoZ を学びたい学生を全国から募集。3 年次編入枠有り(対象:大学建築学部卒又は二級建築士所有者のみ)。
※フェリカ建築&デザイン専門学校は2022 年4 月より名称を上記に変更する
[公式サイト]https://felica.ac.jp
[所在地]群馬県前橋市南町2-38-2
[TEL]0120-343-750